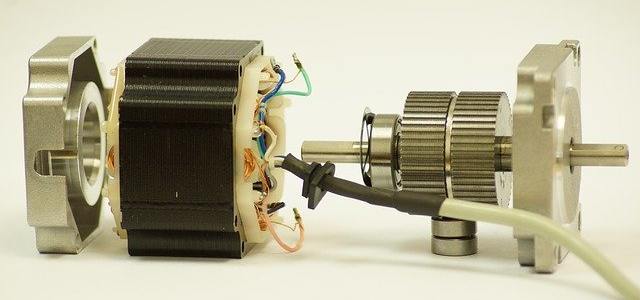コア技術をどのように選定すればよいか分からない、選んだものの自信がないといった相談を受けることがあります。
VUCA時代と言われる先が読みにくく環境変化が著しい今、保有資産である技術の中で、どの技術が将来にわたって価値をもたらすのか、判断することが難しいようです。特に評価指標は多いほど漏れがなく、よい選定ができるのではないかと数十個ほど抽出したものの、どのように選別したらよいか悩むことがあります。評価指標の数は、コア技術の管理業務がルーティン化していくにつれ、増える傾向がありますが、多すぎると重要な指標が埋もれるなど管理しにくくなります。
そこで今回は、コア技術を選定する上で、まずは押さえてほしい3つの指標について解説します。
- 優位性
コア技術は、競合と比較して優れている必要があります。
優れていることで、製品価値を高めることができるからです。逆に言えば、製品価値につながらない技術は選定の土台に載せません。
保有技術が競合と比較して、優位であるか否かを評価するにあたり、競合は同じ技術もしくは類似技術を保有している企業・団体を選択します。
優位性を判断する対象物は、特許や論文といった文書とリバースエンジニアリングなどによる実験データが活用されます。 - 継続性
コア技術は、現在のみならず将来にわたって活用される必要があります。
継続的に製品価値をもたらす技術であれば、開発の投資が可能です。開発を継続できれば、コア技術をさらに改良・進化させることにつながり、より優位性や独自性を担保する可能性が広がります。逆に言えば、ちょっとした改良・改善に限り、大きな進化が難しく代替技術が容易に考えられる技術は選定の土台に載せません。
継続性の基準はいくつか考えられますが、代表的な基準として製品ライフサイクルがあります。例えば、製品ライフサイクル=5年であれば2サイクル以上といった基準を作るといったケースが該当します。 - 独自性
コア技術は、競合が少ない独自なものである必要があります。
先に示した優位性や継続性にも深く関わりますが独自の技術ではない場合、真似されやすい、つまり新規参入の脅威を常に意識しなくてはいけません。
真似されやすい技術は多くの競合を生み出す可能性があり、結果として、陳腐化してしまい製品価値につながる強みとは言えなくなることがあります。
一方、独自性の追求には注意が必要です。唯一無二を目指すあまり製品価値につながらない技術も多く目にします。コア技術を選定する際には、独自性に偏重しすぎず継続性や優位性とバランスを取って評価する必要があります。
以上のように3つの指標を使い、保有技術の一次選定を行った上で、自社の価値観に応じた指標をいくつか追加することで、ステークホルダーが納得するコア技術の選定を実現します。
当社では、自社に合ったコア技術選定の支援を行っています。お気軽にお問い合わせください。